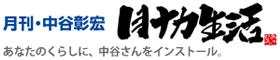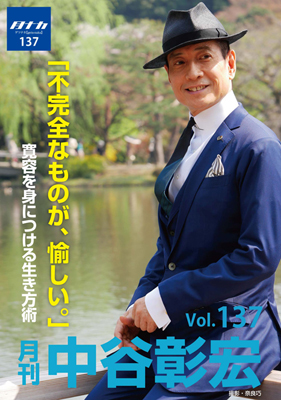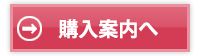月刊・中谷彰宏137「不完全なものが、愉しい。」――寛容を身につける生き方術
完璧を求めてしまっていませんか、他者にも自分にも。人間関係が損なわれてしまうのは、他者に完璧を求めるから。
メンタルの失調を残ってしまうのは、自分に完璧を求めるから。
「完璧では、成長できない。不完全だから、成長できる。
完全より不完全、確実さよりスピード。」と中谷さん。
不完全に対する寛容性が、私たちの能力を高めてくれます。
他人にも自分に寛容になる方法、中谷さんから伺いました。
★こんな方にお奨めです♪
□自分にも、他人に完璧を求めてしまう方。
□良好な人間関係が長続きしない方。
□クリエイティビティを発揮したい方。
○「完璧性より、クリエイティブ性。」(中谷彰宏)
その昔、絵画の価値は、その写実性でした。
カメラのない時代、絵は写真の代用をしていたからです。
カメラができると、絵の価値は大転換を遂げました。
画家の「クリエイティビティ」が問われるようになったのです。
「完璧性を求めるのは、写実を求めるのと同じ。
指示通りでは、クリエイティブ性は生まれない。」と中谷さん。
クリエイティビティを発揮するためには、指示を超えた判断力。
当意即妙のアドリブ力が、クリエイティブ性を生むのです。
○「完璧な人は成長しない。完璧より成長。」(中谷彰宏)
「完璧な人とは、失敗のない人」というのが日本社会の認識。
ところが、クリエイティビティの国・アメリカでは違います。
「失敗のない人」とは、チャレンジしない人、成長しない人。
「完璧志向の人間は成長しない。下がるしかない。
不完全な人間は成長できる。上がるしかない。」と中谷さん。
自分の不完全さに自覚できる人が成長できる。
あなたの「不完全さ」は、どこにありますか?
○「やってもらっている人間は、不幸感を持つ。」(中谷彰宏)
自ら、まとめ役を引き受ける人と、つねに参加者でいる人。
人には、この2種類のタイプがいます。
「幹事をやったことのない人が、文句を言う。
被害者意識ばかりが立ち上がる、不幸な人。」と中谷さん。
月ナカでよく話題にのぼる、「当事者」と「傍観者」です。
当事者となることで、多くの経験値を積むことができますし、
「やってもらっている」という感謝の気持ちを持つこともできます。
一度の人生、せっかくなら当事者でありたいですね。
○「折衷案は、最低。」(中谷彰宏)
A案とB案、どちらを採用するかで、なかなかまとまらない会議。
その時、「では、間をとって、折衷案といきませんか?」というひと声。
妥協の産物「C案」は、最悪なものになってしまうのが現実です。
「折衷案ではきりがない。長いタイトルの本は折衷案。
上司が言った言葉が削れないでいる。
どちらかを選ぶことで、覚悟が鍛えられる。」と中谷さん。
迷ったら、両方採用でも両方却下でもはなく、一つに決める。
こんな鍛錬を通じて、「ここ一番」の決断力が養われるのです。
○「時間がかかった正解は、不正解。」(中谷彰宏)
消防庁の標語に「すばやく、正確に」というものがあるそうです。
消防の仕事には、どちらも大切な心構えですが、これも折衷案。
「やっぱり、すばやさ。正確でも遅ければ意味がない。
両者を盛り込むことで、大事なことがぼやけてしまった。
時間がかかった正解は、不正解。」と中谷さん。
正解にこだわるよりも、すぐに始める、終わらせる。
これが、プロフェッショナルの覚悟なのですね。
○「不完全さが、クリエイティビティの源。」(中谷彰宏)
大家として名を成した画家、彫刻家、音楽家たち。
生まれながらに「完全」であった彼らは、さらに磨きをかけて、
巨匠と呼ばれるようになった――という認識は、じつは思い込みでした。
「セザンヌや横山大観が巨匠になったのは、絵がへただったから。
不完全だから工夫できる。工夫で彼らは巨匠になった。」と中谷さん。
「下手」を工夫で磨くことで、「才能」に昇華するのですね。
○「寛容性が、世の中を豊かにする。」(中谷彰宏)
事件、事故、過失――問われるべき罪はありますが、
だからといって、寄ってたかって非難し、攻撃するのは別問題。
「おたがいの不完全に、つながりが見つけ出せる。
不完全に対する寛容性が、世の中を豊かにする。」と中谷さん。
見ず知らずの人にも、すっと話しかけられる。
よく知らなくても、ふつうにつきあえる。
不完全さがあるからこそ、人は快適に生きられるもの。
水清ければ魚棲まず。
不寛容ブーメランは、いずれ自分に返ってくるのです。