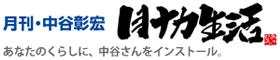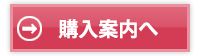月刊・中谷彰宏135「自分だったらどうするかを考え続ける。」――当事者意識から逃げない仕事術
仕事ができない人に欠けているのが「観察力」。同じ情景を見ていても、受け取るものがまるで違う。
同じ場面に遭遇しても、学びの量がまるで違う。
では、どうすれば、観察力が身につくのでしょうか?
それは「当事者意識」を持つこと。
この店のサービス、自分だったら、どう変えていくか。
この仕事、自分だったら、どうやって工夫していくか。
常に「自分だったらこう改善する」と考える習慣を持つ。
これが当事者意識を持つということ。
仕事に前のめりになる心構え、中谷さんから伺いました。
★こんな方にお奨めです♪
□いまの仕事に前向きになれない方。
□いまの仕事が楽しめない方。
□もっと売上と利益を伸ばしたい方。
○「マナーを作れば、ビジネスになる。」(中谷彰宏)
オリンピックの正式種目でもあるスノーボード。
ところが、登場したてのときには「不良(?)の遊び」でした。
それが市民権を得られたのは、マナーのおかげ。
「法律も道徳も変動する。だけど、マナーは変わらない。
マナーができたことで、認められるようになった。」と中谷さん。
認められたいのなら、マナーを身につけること。
実力よりもマナー。マナーも実力の内なのですね。
○「抜け出すために、腕を磨こう。」(中谷彰宏)
「やっている仕事に、やりがいや誇りを持てない……」
そんな方に向けて、中谷さんはこうアドバイス。
「卒業したいと思うのなら、腕を磨くしかない。
自分で選択できるくらい上達すれば、抜け出せる。」
せっかくありつけた「いやな仕事」なら、そこから吸い尽くす。
このくらいの気構えで臨めば、いやな仕事は学びに満ちた仕事に。
気持ちの切り替え一つで、目の前の光景は一変するのですね。
○「自分の方程式を持とう。」(中谷彰宏)
一部の面倒くさい患者さんの対応に困っているクリニック。
ベテランの受付さんが、アドリブで対応してきたのですが、
これもそろそろ限界。しだいにメンタルをやられてきました。
そこで、院長が導入したのが「方程式」。
「仕事での問題には、せいぜい何通りかのパターンしかない。
自分の方程式を持てば、それに対応できる。」と中谷さん。
問題のパターンを分析し、対応のパターンを考える。
そのために必要なのも、「観察力」なのですね。
○「工夫すると、仕事が楽しくなる。」(中谷彰宏)
階層が上に行くほど、自分の意志を反映できます。
言い換えれば、工夫を実践することが可能になります。
その点、下っ端――階層が低い人達はそうではありません。
上からの指示やマニュアル通りにやらなければなりません。
でも、そんな状況でも、工夫ポイントを見つけ出す人がいます。
そういう人が「上」に上がっていくのがビジネス社会。
仕事を楽しめないのは、工夫を諦めているからかもしれませんよ。
○「傍観者ではなく、当事者になろう。」(中谷彰宏)
あるレストランで、2人は同じサービスを受けました。
1人の「傍観者」は、サービスを批評して、良し悪しを語りました。
1人の「当事者」は、サービスを観察して、学び尽くしました。
この両者、十年、二十年の歳月の中で、どれだけ差がつくでしょうか。
「世の中には、傍観者と当事者しかいない。
僕はスナックの息子だから、どこに行っても当事者。
ここを任されたらどうするか、いつも考えている。」と中谷さん。
成長する人は、学べるポジションに身を置くのですね。
○「一流の仕事は、観察力が違う。」(中谷彰宏)
車内販売の売り子さんでも、売れる人と売れない人がいます。
「売れる子は、後ろのお客さんに意識を向けている。
眼の前のお客さんとのやり取りを通じて、語りかけている。
だから、その場で両側のお客さんに売れる。」と中谷さん。
中谷さんの観察力には、驚かされますね。
もっとも、その売り子さんも相当の力量。
売れている先輩を観察しながら、技を磨いていったのでしょうね。
○「プロは、素人のふりをする。」(中谷彰宏)
相手を油断させた人が勝つ。これは、投資でもギャンブルでも同じ。
プロのギャンブラーは素人のふりをして場を盛り上げるそうです。
それは、ディーラーもお見通しで、出来レースを演じる。
結局、巻き上げられるのは、そこに集まってきたカモたち。
「プロは、素人のふりをする。本当の素人が集まってきたら、
さっと身を引いて、利益を確定する。」と中谷さん。
プロになるかカモになるか、これも観察力次第なのですね。