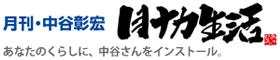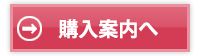月刊・中谷彰宏126「リズム感のある人が、うまくいく。」――心に詩を持つ生き方術
がんばっているのに、結果が出ない――なぜか、人間関係がギクシャクしてしまう――
そういう方は「リズム感」が欠けているからかもしれません。
リズムにのっていれば、仕事はうまくいきますし、
リズムがよければ、誰とでも意気投合できるものです。
では、どうしたらリズム感をよくすることができるのでしょうか。
それは、「広い視野」と「先読みする力」を身につけること。
スマホを凝視していては、周囲で何が起こっているかわかりません。
目の前の仕事に追われていては、先読みする余裕がありません。
そう、リズム感とは、広く見渡すことで獲得できるのです。
リズム感を獲得する方法、中谷さんから伺いました。
★こんな方にお奨めです♪
□人間関係がギクシャクしてしまう方。
□仕事がスムーズに運ばない方。
□毎日を快適に過ごしたい方。
○「仕事ができる人は、リズム感がある。」(中谷彰宏)
「一行で改行しているのも、リズムをよくするため。
中谷本をまねしても、まねできないのがリズム感。」と中谷さん。
接続詞は、リズムを損ねるので、できるだけ使わない。
リズムにのって、一気に、最後まで書き上げてしまう。
それから、「読者のリズム感」に切り替えて直していく。
これが、中谷さんの執筆作法なのだそうです。
勢いやノリ、これがリズムをつくるのですね。
○「リズム感は、視野の広さと先読みで決まる。」(中谷彰宏)
リズム感がいい人とは、どのような人なのでしょうか。
「リズム感は、視野の広さと先読みで決まる。
お寿司屋さんで、いいお客さんは、注文する間がいい。
お店の状況が見えているし、展開を読めている。」
ご主人や他のお客さん、さらには時間帯や天候まで。
「フィールド」全体を見下ろす視野が問われる注文の間。
お寿司屋さんで、リズム感を磨く練習をしてみましょう。
○「七五調で、注文しよう。」(中谷彰宏)
お寿司屋さんで、リズム感を磨く練習法をご紹介します。
それは、「七五調」で注文する――です。
「サバと、えーっとゲソと…うーん、アジ。あと、コハダも」
こんな注文をしていませんか(笑)。
職人さんは、反復して注文を記憶するので、これは混乱の元。
こんなときは、「サバとイカゲソ、アジコハダ」
こんなふうに注文すると、リズムがよくなりますね。
○「後ろから、語りかけよう。」(中谷彰宏)
「大きい声で怒鳴るより、小さな声で囁こう。」と中谷さん。
今回の収録でも、語りかけのテクニックが紹介されました。
「美容師さんの言うことを、なんとなく信じてしまうのは、
後ろからくるから。後ろから語りかけよう。」と中谷さん。
大声ではなく、小さな声で。
真正面からではなく、後ろから。
この技が、あなたの言葉に「説得力」を持たせるのです。
○「会話力は、リズム感で決まる。」(中谷彰宏)
リズム感ある会話で大事なことは、振り返らないこと。
「終わった話をもう一回持ち出したり、
同じ話を二度するのも、リズムが悪くなる。
そういう間が悪い男は、女性にモテない。」と中谷さん。
どんどん前に進んでいくスピード感がリズム感。
正確性を追求したり、相手の反応すらもお構いなし。
振り返らずに、話を先に進めていきましょう。
○「感じがいい人は、リズム感がある。」(中谷彰宏)
電車やエレベーターといったパブリックスペースで、
感じのいい人は、リズム感があります。
「スマホを見ていると、周囲が見えなくなる。
エレベーターの扉をおさえてくれている人に、会釈もしない。
感じがいい人は、全体が見えている。リズム感がある。」
周囲に人がいるときには、スマホから目を離し、
イヤフォンも耳から外すのがマナーなのですね。
○「詩を朗読すれば、間がよくなる。」(中谷彰宏)
詩は文字で書かれていますが、じつは音楽に近かったのです。
「詩が味わえる人は、リズム感がある人。
リズムは、指で数えられない。口の中で転がして、つかむもの。
文章と音楽の中間にあるのが詩。」と中谷さん。
もし、「間が悪い」ことでお悩みでしたら、詩の朗読。
声に出して読むことで、リズム感が躍動してきます。
詩を朗読することで、タイミングのいい人になれるのです。