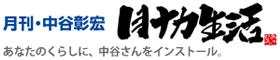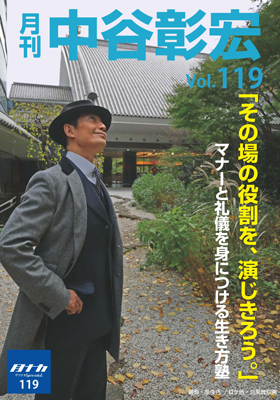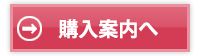月刊・中谷彰宏119「その場の役割を、演じきろう。」――マナーと礼儀を身につける生き方塾
「感謝」は大切です。でも、感謝の気持ちで終わらせてしまっていませんか?感謝とは、言ってみれば「相手」とは無関係な、あなたの心の中での営み。
具体的に伝えなければ、その気持は「相手」に伝わりません。
感謝の気持ちを具体的に伝えること、これが「礼儀」と中谷さん。
でも、言葉に出すには勇気が必要ですし、お礼をするのは面倒くさい。
だからこそ、その「ひと手間」が威力を発揮するのです。
さらに言えば、そのひと手間を無意識のうちにやれる心構えが「マナー」。
そう、マナーとは礼儀を条件反射で行ってしまうような習慣付けなのですね。
感謝の気持ちを具体化して、コミュニケーションを深化させる方法、
中谷さんから伺いました。
★こんな方にお奨めです♪
□謝ることができない方。
□マナーと礼儀で、突破したい方。
□役立ち感を得たい方。
○「人生で、ヤマは張れない。」(中谷彰宏)
老後の準備には、どんなことをしたらいいのか?
こういう問いは、歳を重ねるごとに、自問する機会が増えるものです。
でも、中谷さんはこうおっしゃいます。
「人生で、ヤマは張れない。老後の準備より、仕事の準備をしよう。」
不確定要素に満ちあふれた遠い未来の準備をするより、
目の前にある現実に対して、具体的な対処をする。
結果として、これが「老後の準備」になるのだから人生は面白い。
目の前の仕事に、全力投球しましょう。
○「マナーは、作法ではない。」(中谷彰宏)
マナーと言うと、まず思い浮かべるのがテーブルマナー。
でも、テーブルマナーは、じつはマナーというより作法。
ここで注目すべきは、マナーと作法は異なるという点と中谷さん。
テーブルマナーは言ってみれば作法。
茶道や華道のように、非日常の空間のお約束事。
ところが、エレベーターや新幹線には、確立した作法はありせん。
でも、こういうところだからこそ、その人のマナーが如実に表れます。
作法なき世界で、自分の美意識にのっとった行動をとる。
そんなストイックな精神のありようが、マナーというものなのです。
○「マナーで、運不運が決まる。」(中谷彰宏)
そもそもマナーとは、なぜ必要なのでしょうか?
円滑な人間関係から充足感を得るため。
美しい生き方を追求する満足感を得るため。
これらも重要な要素ですが、もう1つの重要な側面を忘れてはなりません。
それは、「運」をよくするため。
マナーがいいと運が良くなり、マナーが悪いと運が悪くなるのです。
人は、私たちの行動を意外と見ているものです。
マナーのいい人は言祝がれ、マナーの悪い人は呪詛(?)をかけられる。
人から陰に陽にかけられるエネルギーが、実は運気というものなのです。
○「謝れるのが、余裕の表れ。」(中谷彰宏)
「ごめんなさい」「間違っていました」と言ってしまうと、
自分の「負け」や「誤り」を認めてしまうことになる――
そう思っている方は、この機会に、認識を改めましょう。
「謝れるのが余裕。そこに、器が出る。」と中谷さん。
そう、自信があるから謝ることができるのです。
言い換えれば、謝れない人は自信のない人であり、
謝れないことで、さらに自己肯定感が減退していきます。
「謝る」とは謝罪ではなく、相手への譲歩。
強い人にしか持ち得ない余裕の表れなのですね。
○「感謝している人ほど、礼儀知らずになる。」(中谷彰宏)
心で感謝しているから、わざわざ言葉にして相手に伝える必要はない。
――こういう人は、たとえ感謝の気持ちを持っていても、礼儀知らず。
それは自己満足であり、成熟した人間関係は結ぶことができません。
「礼儀は、その日の内にやらなければならない。
きついことをするのが礼儀。感謝していなくても、
礼儀を知っている人が勝利する。」と中谷さん。
心の中で「ありがとう」と100回唱えるより、お礼のメールを送る。
礼状を書く――こんな具体的な行動が「礼儀」というもの。
感謝を礼儀として具体化できるかに、誠実さが表れるのですね。
○「与えられた役割を、演じきろう。」(中谷彰宏)
「自分に正直に生きる」とは、とても耳ざわりのいい言葉です。
でもこれは、往々にして「わがまま宣言」だったりします。
「私は好きなことしかやらない。嫌なことはやらない。」
学芸会で、自分が主人公でなければ嫌だと言う小学生と変わりません。
こんなことでは、社会で活躍したり成功を掴むことは到底不可能。
なぜなら、成功者とは、与えられた「役割」を演じている人だからです。
希望する「役割」でなくても、真剣に淡々と演じる。
そういう人が引き上げられ、担ぎ上げられているのが現実です。
「自分に正直に生きる」のか、それとも「役割を演じきる」のか。
どちらを選ぶかによって、人生は大きく変わってくるのです。
○「役割に、罪悪感を持つ必要はない。」(中谷彰宏)
あるときは人気者、あるときは憎まれ者のヒール。
役者さんは求められるまま、じつにさまざまな「役」を演じます。
だからといって、英雄を演じるときに天狗になり、
悪役を演じるときに罪悪感にさいなまれる――そんな役者さんはいません。
人間社会も、いわば一場の舞台。
「自分も一役者なのだ」と割り切ってみてはいかがでしょうか。
「その場その場で役割が変わる。役割は、ふだんの性格とは関係ない。
嫌われ役をやるのも役割。そこで罪悪感を感じる必要はない。」と中谷さん。
自分の感情を棚上げして、求められる役を淡々と演じきる。
これが、燃焼感あふれる人生には不可欠な心構えなのでしょうね。