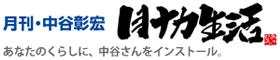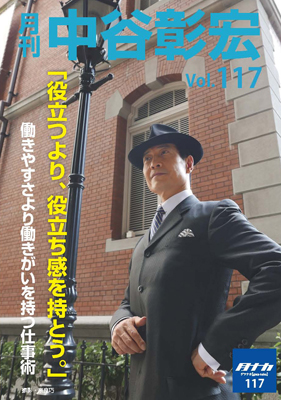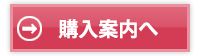月刊・中谷彰宏117「役立つより、役立ち感を持とう。」――働きやすさより働きがいを持つ仕事術
幸不幸に、数値化できるようなモノサシはありません。目の前の現象をどうとらえるか、私たちの「解釈」次第です。
同じ状況に出くわしても、それをラッキーととらえられるか、
それとも、アンラッキーであるととらえてしまうか。
ここに「ラッキー感度」が表れます。
では、どうしたらラッキー感度を高めることができるのでしょうか?
それは、すべてをラッキーとして解釈してしまう「物語力」を磨くこと。
映画や小説から、数多くの「物語」を仕入れておく。
いま問われている「神様のテスト」は何なのかつねに考える。
そうすれば、苦境も見せ場。苦笑いしながら向き合うことができます。
すべての状況に感謝できるマインドセット術、中谷さんから教わりました。
★こんな方にお奨めです♪
□つい愚痴っぽくなってしまう方。
□自分は、不幸であると思っている方。
□苦境を、学びの機会にしたい方。
○「働きやすさより、働き甲斐。」(中谷彰宏)
いまの若者は、「働きやすさ」を志向しているそうです。
「ブラック企業」というのは、働きにくい職場を指すのかもしれません。
でも、ひと昔前は違いました。
私たちの年代以上は、働きやすさより「働き甲斐」を求めたものです。
給料が少なかろうと、休みもほとんどなく徹夜続きであろうと、
上司のパワハラに遭おうと、仕事に「やり甲斐」を求めたのです。
これも時代の流れですから、しかたがないのでしょうが、
「働きやすさ」を求めると、不平不満が出やすくなるから困ったもの。
結局、「働かない」というところまで行ってしまいかねません。
「働きやすさより、働き甲斐。」と中谷さん。
働き甲斐を追求すれば、仕事のつらさなんて吹き飛んでしまうのです。
○「幸福感は、夢中度で決まる。」(中谷彰宏)
仕事、恋愛、趣味――何かに夢中になることは、
私たちに、幸福感を与えてくれます。
夢中になる対象がない人生ほど、空虚なものはありません。
そして、この「夢中力」は、子供のときに決まるそうです。
「『早くしなさい』は、クリエイティビティの敵。
子供がボーッとしているのは想像している瞬間。邪魔しない。」
ボーッとしていたり、没頭していたりするときに、
「夢中力」がつちかわれているのですね。
ボーっとする時間、没頭する時間をたいせつにしましょう。
○「好きなことは、天職ではない。」(中谷彰宏)
「好きを仕事にしよう」とよく言われますが、中谷さんは違います。
「好きなことは、天職じゃない。20代は、頼まれたら何でもやってみる。
『意外に嫌いじゃない』ことが天職になる。」
面白いもので、人は、やりたくないことをやるときには、
その仕事に「やり甲斐」を見出そうという心理が働くそうです。
つまり、やりたくない仕事や働きにくい環境のほうが、
「働き甲斐」が見つかるというのです。
給料が悪い、感謝されない、そんなブラック仕事が、
あなたの可能性を開花させてくれるかもしれません。
○「働き甲斐とは、役立ち感。」(中谷彰宏)
では、働きがいとは、どんなときに得られるのでしょうか。
それは、誰かの役に立ったときです。
たとえば、カラオケ。
うまくないのなら、真っ先に歌いましょう。
「下手な人が最初に歌うと、あとが楽。
歌唱力という能力のなさが、役立ち感を生んでいる。」と中谷さん。
「能力=役立つ」という図式は必ずしも成立しないのです。
「能力のなさ」を役立てる方法に、チャンスがありそうです。
○「期待感が強いから、不幸だと思ってしまう。」(中谷彰宏)
「奇跡」についてどんな考えをお持ちですか?
「すべてが奇跡」あるいは「奇跡なんて一つもない」
――こういうスタンスの方は、幸せであると中谷さん。
「奇跡はある。でも、私の周りにはない……」と考える人は不幸です。
「今はないけれど、いつか奇跡がやってくる」、
そういう期待感が、日常を暗いものにしてしまうからです。
そんな期待を持つよりも、日常に「意味」を見つけ出しましょう。
すべてに「意味」を感じられる人は、すべてが奇跡となります。
すべてを自己責任で解釈する人は、奇跡なんてないと考えます。
ともに、運不運に振り回されていないところが幸せなのですね。
○「習慣にすれば、淡々とこなせる。」(中谷彰宏)
部屋の掃除にしても、領収証の整理にしても、
「やる気」を出して、一気にまとめて片付けようとすると、
なかなかやる気になれないものです。
「モチベーションを上げなくてもできるのが習慣。
意欲はあるけど、必死ではないのが習慣。」と中谷さん。
ジョギングでも、掃除でも、日記でも、早起きでも、
「奮起」しないで、日常生活に盛り込んでしまう。それが習慣。
いったん習慣にしてしまえば、やらないのはかえって気持ち悪い。
「やる気」より「習慣」のほうがエネルギー効率がずっといいのです。
○「捨てれば、意欲がわいてくる。」(中谷彰宏)
若くて、何事にも意欲的な時期は、手を広げようとするものです。
その時の「成功体験」が捨てられず、いつまでも手を広げる人がいますが、
これは逆効果。意欲は、どんどん失われていってしまいます。
「持ち物や執着を減らせば、意欲がわいてくる。
皿洗いでも、アイロン掛けでも、何でもいいから一点突破。
一つあるだけで、意欲的になれる。」と中谷さん。
散漫にならないで、対象を絞り込んで集中する。
これが、いつまでも意欲的に生きるためのコツなのですね。