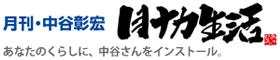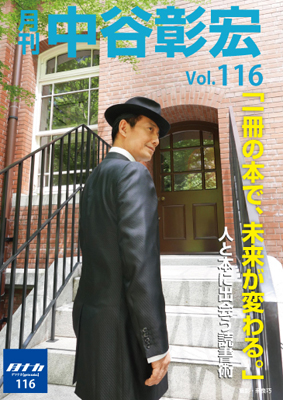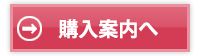月刊・中谷彰宏116「一冊の本で、未来が変わる。」――人と本に出会う読書術
余裕がある人はかっこいい。余裕のない人はかっこ悪い。いかにして余裕を身にまとうか――ダンディズムとは、その流儀といえます。
しかし、余裕とは「持とう」と決意したところで、持てるものではありません。
具体的なテクニックや日頃からの思考習慣や生活習慣の集大成だからです。
その境地に確実に近づけてくれるのが読書。
ビジネス書を通じて、仕事の技法を修得する。
自己啓発書を通じて、自分の意識を新たなものにしていく。
歴史書を通じて、社会の移り変わりを予見する。
リラックするするための読書、元気になるための読書もあります。
そう、本をめぐる世界の豊かさが、「余裕」をもたらしてくれるのです。
かっこよくなるための本の読み方、中谷さんから伺いました。
★こんな方にお奨めです♪
□すぐにいっぱいいっぱいになってしまう方。
□読書を通じて、もっと深い世界に到達したい方。
□やる気に波がある方。
○「余裕のなさが、かっこ悪さ。」(中谷彰宏)
人にはそれぞれ行動を決定づける基準があります。
よく中谷さんが「価値軸」とおっしゃいますが、まさにそれです。
ある人は、損得で判断します。ある人は、楽かどうかで判断します。
でも、なかには、かっこいいかどうかで行動する人もいます。
「かっこいいかどうかを考えるのは、余裕がある証拠。
その余裕が、さらにかっこよくしてくれる。」と中谷さん。
余裕を持てば、かっこよくなる。かっこよくなれば、さらに余裕ができる。
こんな好循環を獲得したいものですね。
○「難しい局面を体験することが、キャリアになる。」(中谷彰宏)
では、余裕の好循環は、どうしたら獲得できるのでしょうか?
それは、修羅場をたくさん体験すること。
つぶれた会社に最後まで残って、残務処理を成し遂げる。
「負け戦」を引き受けて、ひとりで戦い続ける。
こんな人たちが、成功を掴んでいるのは、歴史をみても明らかです。
「秀吉は、絶体絶命の殿軍(しんがり)を引き受けたから、
その後の人生が開けた。」と中谷さん。
難しい局面を体験したことが、名誉の経歴になるのですね。
○「社内評価より、社外評価。」(中谷彰宏)
ふしぎなもので、社内評価と社外評価は裏腹になりがち。
社内で評判のいい人は、意外と社外では通用しない。
一方、社内での評判が悪い人が、社外で名を馳せている。
――こんなことはよくあります。
これは、社内と社外での価値軸が真反対だから起こる現象です。
「外」での評価につながるアグレッシブな活躍は、
「内」では往々にして、「出すぎたまね」として嫌われます。
でも、「内」ばかり見ていては、真の実力は身につきません。
「外」を意識することで、いつまでも成長できるのです。
○「食わず嫌いに、チャンスがある。」(中谷彰宏)
翻訳書には手が伸びない。経営書が苦手。小説は読む気が起こらない。
読書には、人それぞれの志向性が表れます。
でも、今の状態をよしとしていれば、成長の機会を逃してしまいます。
「食わず嫌いに、チャンスがある。」と中谷さん。
今まで避けてきた読書ジャンルに、あえてトライしてみましょう。
結果的に、そのジャンルが好きになれなくてもいいのです。
そういうトライにこそ意味があるのですから。
「『この1行』に出会えれば、それでいい。」と中谷さん。
そんな「1行」との出会いが、読書の醍醐味なのですね。
○「素直だと、運命の本に出会える。」(中谷彰宏)
「好きなこと」の大切さを、中谷さんはよくおっしゃいます。
でも、「好きなこと」だけにこもってしまうと、プロにはなれません。
「読書には素直さが大事。黙って読めるのは才能。」と中谷さん。
周囲の読書家からの推薦図書を読んでみる。
たとえ気乗りしないものであっても、黙って読んでみる。
そういう柔軟性が、「好きなこと」に磨きをかけていき、
しだいに「専門分野」として確立していくのです。
「オタク」が「専門家」になるかどうかは、この瞬間で決まります。
素直さ、これがプロフェッショナルに不可欠な資質なのですね。
○「移動すると、モチベーションが上がる。」(中谷彰宏)
集中できない。モチベーションが上がらない。
そんなとき、静かな場所に、一人ひっそりこもるのは逆効果。
そういう環境では、意外と集中できないものです。
適度な雑音があったほうが集中できるのが実際のところです。
最近、コワーキングスペースが増えてきていますが、
その背景には、こうした事情があるのでしょう。
みんながんばっている場所に身を置くと、自分もがんばれる。
自習室や図書館の「白熱空間」は、やる気を高めてくれます。
学生時代、中谷さんは、図書館をはしごしていたそうです。
「白熱空間」に「移動」を絡めれば、集中力アップ間違いなしです。
○「読書は、勉強ではない。衣食住の一部。」(中谷彰宏)
「読書=勉強」という先入観を、多くの人は持っています。
でも、これは学生時代からの認識を変えられないでいる証拠。
そのマインドが、読書を遠ざけてしまっているのです。
「読書は、勉強ではない。衣食住の一部。」と中谷さん。
ご飯を食べたり、お風呂に入ったりするように本を読む。
リラックスするために本を読む。元気になるために本を読む。
本とは、心に栄養をもたらすサプリメントなのですね。