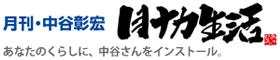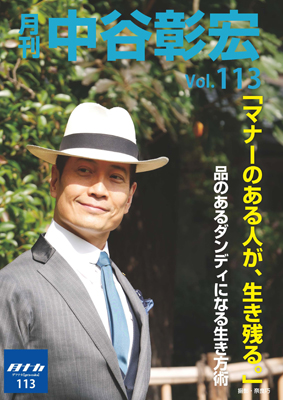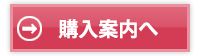月刊・中谷彰宏113「マナーのある人が、生き残る。」――品のあるダンディになる生き方術
生き延びるための究極戦術、それは「礼儀作法」。専門知識も営業力なんて、礼儀作法の前には無力です。
精神力や健康や体力ですら、礼儀作法の足元に及びません。
マナーが良い人は生き延び、マナーが悪い人は淘汰される――これが現実です。
ちょっとした傍若無人な態度が怒りを買い、
ちょっとした気遣いのなさが恨みを買っています。
礼儀作法ができていないことのリスクは、思いのほか大きいのです。
運の悪い人は、こういう小さな怒りや恨みに無頓着です。
こうした恨みが積もり積もって、自分を不幸にすることに気づいていないのです。
運を高めるための礼儀作法、中谷さんから伺いました。
★こんな方にお奨めです♪
□感じのいい挨拶が苦手な方。
□核家族に育った方、核家族を営んでいる方。
□運気を高めたい方。
○「礼儀作法で、品格が決まる。」(中谷彰宏)
同じように刀を差していても、武士と浪人は違います。
違いは「礼儀作法」。
幼少時から、きちんと躾られている武士は、礼儀作法がばっちり。
一方、浪人は、そうした教育機会には乏しい生い立ちです。
これが、武士と浪人の品格の違いに表れているのです。
サラリーマン生活を経験した経営者は、未経験の経営者より、
品格を感じますが、これも根っこが同じかもしれません。
生き延びるためには、礼儀作法が不可欠であると、
サラリーマン生活で学んできたからなのでしょうね。
○「態度が悪いから、チャンスがつかめない。」(中谷彰宏)
プロ野球の落合博満さんが中日の監督に就任したとき、
最初に取り組んだのが、態度教育でした。
態度をよくすることが、技術の向上に必要だと考えたのです。
「態度教育」は当初、批判されてきましたが、結果を出しました。
こうしてみると、礼儀作法のの効果の程が伺えます。
技術と礼儀というと、一見関係ないようですが、
一流の人たちは、その相関関係を熟知しているのでしょう。
技術と礼儀作法、これが上達のための両輪なのですね。
○「パブリックスペースでのマナーを、わきまえよう。」(中谷彰宏)
公私混同について、世の中が厳しくなってきました。
この風潮に鈍感な政治家は、公私混同で追求されたりしています。
公私の区別の大切さは、お金に限ったことではありません。
「礼儀とは、プライベートスペースとパブリックスペースを区別すること。
核家族に育つと、私的空間と公的空間の区別が身につきにくくなる。」と中谷さん。
「家の中でのふるまい」を外でやってしまうのが、マナーの公私混同。
公私のメリハリに、「育ち」というものが出てしまうのです。
子供にはお金を残すのではなく、礼儀作法を残す。
これが上流家庭の相続というものなのですね。
○「ダンディな男は、権利を主張しない。」(中谷彰宏)
いさかいは、権利の主張がぶつかりあって起こります。
列車の肘掛けの奪い合いから、ウェイターの対応に対するクレームまで。
寛容さに欠けると、権利の主張に走ってしまうものです。
「パブリックスペースでは、悪意なく迷惑がかかることがある。
そういう事態でも、平常心を保てるのがダンディな男。」と中谷さん。
何かにつけてクレームをつけたりするのは、器の小さい証拠。
新人さんの不始末に目をつぶる。
こんな見て見ぬふりで、度量は大きくなっていくのです。
○「その一声が、礼儀作法。」(中谷彰宏)
人間関係が和やかになるかギスギスしたものになるか、
それは、「一声」かけられるかどうかで決まります。
「こんにちは」「ありがとう」「お疲れ様」
こうした「一声」は、必ずしも絶対必要なものではありませんが、
こうした言葉ひとつで、場の空気はぐっと変わります。
とはいっても、「その一声」をかけるには勇気が必要です。
挨拶しても無視されたらバカバカしい――そう考えてしまって、
言うのを、ためられってしまう人もいることでしょう。
そこで問われるのがメンタル力。
見返りを求めずに行動できる、そんなメンタル力を培いたいですね。
○「礼儀正しいと、自由度が高まる。」(中谷彰宏)
礼儀作法を無視して、強引に手に入れるのは「身勝手」。
周囲に十分配慮することで、与えられるのが「自由」。
「身勝手」は、いずれ破綻をきたすことは確実です。
世の中うまくできているもので、周囲に「快適」を与えると、
そのお返しに「自由」が与えられるようです。
仕事を前倒しして、関係者を安心させれば、
締め切りやギャラ面での「不自由」から開放されます。
「自由」を獲得するには、こうした配慮、つまり礼儀が第一。
礼儀作法は、快適に生きるための技法なのですね。
○「挨拶できる人が、生き延びる。」(中谷彰宏)
「短期的に生き延びるためには、その場しのぎの嘘。
中期的に生き延びるためには、勉強。
長期に生き延びるためには、礼儀作法。」と中谷さん。
「生き延びる」という目的に対しても、時間軸の違いで、
こんなに対応の仕方が変わってくるのです。
生き延び戦術の中で最強なのが、挨拶。
ふだん言葉を交わす人を優遇するのが、人情というもの。
いざというときに、手を差し伸べられるのはこういう人です。
生き残るのは、挨拶習慣のあるマナー練達者なのです。