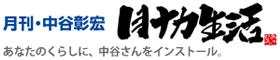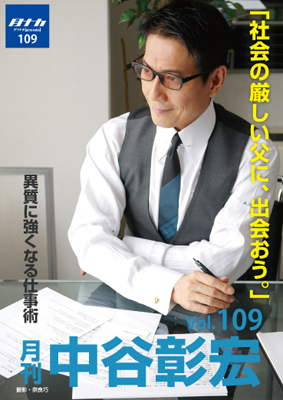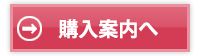月刊・中谷彰宏109「社会の厳しい父に、出会おう。」――異質に強くなる仕事術
いくらでも引きこもることができるのがネット社会。でも、「安住の地」に引きこもっていると、
安住できなくなってしまうのが、現実社会というものです。
つねに、「異質」なものを取り入れながら、成長していく。
苦手意識、理不尽、解釈不能な人たち――
こんな存在が、私たちの頭脳を活性化してくれます。
日々の小さな「異質」が、「安住の地」をもたらしてくれる。
アウェイで戦い続けるための心得、中谷さんから伺いました。
★こんな方にお奨めです♪
□人見知りしてしまう方。
□現状から脱皮したい方。
□断り下手な方。
○「解釈不能な相手に出会おう。」(中谷彰宏)
最近、岡田尊司さんの『人間アレルギー』という本を読みました。
花粉や食べ物のアレルギーのように、特定の人間に対しても、
アレルギーを発症する人間心理について書かれた本です。
本書を読んで、中谷さんのおっしゃることがよくわかりました。
「解釈不能」な人が、自分を高めてくれるのですね。
「異質」との遭遇によって、ショックを受ける。
そのストレスが人間の成長を促すのですね。
○「『異質』で、脳は活性化する。」(中谷彰宏)
「子供が元気なのは、毎日初めてのことをやるから。」と中谷さん。
たしかに、子供の毎日は新しいこととの出会いばかり。
ところが大人になると、だんだんつきあう人や毎日の過ごし方も、
だんだんマンネリ化してきます。
でも、脳の活性化という点では、これはまずい傾向。
「『異質』で、脳は活性化する。」と中谷さん。
新しい世界にふれる日常を、意識的につくり出していく。
それが、前向きに思考できる「健康な心身」をもたらすのです。
○「好き嫌いがないのが、ルーティンワーク。」(中谷彰宏)
淡々コツコツ――そのためにはルーティンワークを確立すること。
中谷さんは、ルーティンワークの大切さをおっしゃいます。
なぜ、ルーティンワークが大事なのでしょうか?
それは「感情」を除外することができるからです。
選り好みしているうちは、プロフェッショナルとはいえません。
プロフェッショナルは、請け負った仕事を淡々と仕上げます。
仕事には、感情を込めずに心を込める。
「好き」「嫌い」「やる気にならない」「気が乗らない」
こんな感情が入り込むのは、まだまだ未熟である証拠なのです。
○「おしゃべりではなく、語ろう。」(中谷彰宏)
「語り」と「おしゃべり」の違いとは何でしょうか?
「語り」は、いってみれば「月ナカ」のような音声コンテンツ。
そのまま録音しても、聴く人のためになるような内容です。
ところが、「おしゃべり」は社交辞令のようなものです。
内容を追求するというよりも、円滑な人間関係に目的があります。
「おしゃべりではなく、語ろう。」と中谷さん。
せっかくの対面の機会、おしゃべりで時間を過ごすより、
音声コンテンツになるような「語り」を楽しみましょう。
○「苦手意識が、脳を刺激する。」(中谷彰宏)
今回のテーマは、脳の活性化です。
脳トレとか、さまざまな脳の活性化のための方法はあります。
でも、いちばん脳が活性化するのが「ピンチ」のときです。
誰でも、ピンチになれば、全力で考えます。
言い換えれば、ピンチのない日常生活を送っていると、
脳は活性化しないまま、機能が衰えてしまうということになります。
「苦手意識」というと、ストレス源と嫌う人がいます。
でも、そういうことが、脳を刺激してくれるのです。
ストレスを感じることをやりましょう。
○「最初に、キャラを固めてしまおう。」(中谷彰宏)
いちばん嫌われるのが、期待させておいて裏切る人。
「行けるかどうか、一日考えさせてください」と言いながら、
「調整してみたんですが……」という人。
「お金貸せるかどうか、ちょっと考えさせて」と言いながら、
「やっぱり貸せなかった……」。こういう人たちです。
「遠回しに、思わせぶりではだめ。
気を持たせないで、即断る。」と中谷さん。
断る勇気を持つことが、よりよい人間関係に必要なのですね。
○「チームワークとは、仲間の努力を無駄にしないこと。」(中谷彰宏)
チームワークを「連帯責任」のように解釈してしまうと、
とても息苦しい人間関係になってしまいます。
そうなると、チームが力を発揮することもできません。
おたがい傷を舐めあうのがチームワークではありません。
それは「負のチームワーク」と中谷さん。
「チームワークとは、仲間の努力を無駄にしないこと。」
仲間がしくじったからと、あわせて力を抜くようなことはしない。
仲間の無念を晴らすために、自分が挽回しようとがんばる。
そういう人間関係が、「正のチームワーク」なのですね。