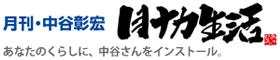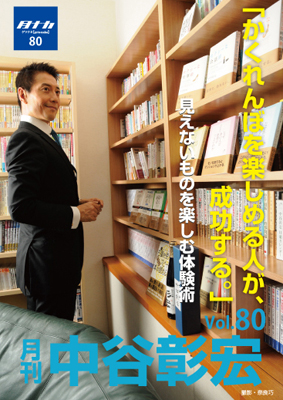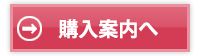月刊・中谷彰宏80「かくれんぼを楽しめる人が、成功する。」――見えないものを楽しむ体験術
子供は、遊びを通じて多くのことを学びます。遊びを通じて、協調する力を身につけていきます。
遊びを通じて、他者を受け入れる寛容さを身につけていきます。
遊びを通じて、新しい枠組みを作る創造力を身につけていきます。
子供時代につちかわれた能力は、実社会にそのまま生かされます。
幸せな家庭運営から友達とのつきあい、そして経済的な成功。
そうです、子供時代、十分遊んだ人たちは、
とても豊かな人生を送っているのです。
「そんなこと、今さら言われても……」という方、
今からでもけっして遅くはありません。
これから「子供時代の遊び」を追体験すればいいのです。
そのための方法、中谷さんから伺いました。
★こんな方に有効です♪
□もっと高い意識レベルに到達したい方。
□子供時代、遊び損なった方。
□ワクワクドキドキする毎日を送りたい方。
○「健康のレベルは、交友関係のレベル。」(中谷彰宏)
誰でも自分の同じレベルの人を友達になります。
お金持ちはお金持ちと友達になります。
健康への意識が高い人は、同じタイプの人と友達になります。
「自分の体脂肪率は、友人五人の平均値。」と中谷さん。
サラリーマンは自分の不健康さを自慢(?)しますが、
自分で仕事をしている人は、健康度をアピールします。
あなたの所属する世界の人たちの健康意識はいかがですか?
○「映画で味わうのは、感情のやりとり。」(中谷彰宏)
映画をストーリーとして観るのは、一回目。
二回目になると、「つくり」に目を行き届くようになります。
では、三回目になると、どうなるのでしょうか?
「三回目は、感情のやりとりを観る。」と中谷さん。
登場人物に憑依して、自分の感情として感じる。
人生を変えるような映画に出逢うためには、
「いいな」と思ったら、最低もう二回は観ること。
これが「映画を味わい尽くす」ということなのですね。
○「一つの体験が次の体験につながるのが、子供の遊び。」(中谷彰宏)
子供の時の遊びは、豊かな人生を送る上でとても重要。
なぜ重要なのか、中谷さんはこう指摘します。
「工夫がある。共感がある。仲直りがある。」
野球をやるにしても、場所がない。人数が足りない。
こういう時にひと工夫。
透明ランナー。アーケードにのってしまったらチェンジ。
足手まといの「みそっかす」も仲間に入れてあげる。
ケンカしても仲直りする。ボールでガラスを割ったら謝る。
ゲームに溺れたり、塾に通っていては、
なかなか体験できないことばかり。
骨太の人格は、子供時代の遊びで完成していくのですね。
○「マナーが集積すると、文化になる。」(中谷彰宏)
遊びには、ルールが必要です。
ルールは子供たちが自分たちで作り上げていきます。
ルールをつくる上では、マナーがその基礎となります。
相手を思いやったり、基本的な礼儀を知らなければ、
仲間で共有できるルールを生み出すことはできません。
「マナーが集積すると、文化になる。」と中谷さん。
ここで言う「文化」は「意識」と言い換えられます。
「意識」は、子供時代の遊びによってもたらされる。
今から追体験するには、もう一度「遊ぶ」ところから。
これが中谷さんの言う「好きなことに没頭する」ことなのです。
○「『斜め』の人間関係が、人を成長させる。」(中谷彰宏)
昔は「斜め」の人間関係が豊かでした。
近所のおっちゃんは、いらずら者をどやしつけました。
おばちゃんは、泣いている子にアメ玉をあげました。
「斜め」上の人たちが、子供たちの情操を支えていました。
ところが、地域社会が崩壊し、状況は一変。
今では、仲間や同僚という横の人間関係と、
上司・部下という縦の人間関係に収斂されてしまいました。
縦横だけの人間関係に陥っている方は、今こそ趣味の世界。
趣味の世界は、「斜め」の人間関係をもたらしてくれます。
○「主人公には、弱点が必要。」(中谷彰宏)
女性に弱い、お酒に弱い、朝が苦手。これが「弱点」。
一方、「欠点」は、残虐、薄情、冷酷という性格上の欠陥。
ルパンは峰不二子には弱いですが、平気で人を殺したりしません。
「弱点」を持つのが主人公。「欠点」を持つのが悪役。
「弱点」があるからこそ、その人は愛されます。
「欠点」で愛されることはありません。
「欠点」を克服して、「弱点」を包み隠さない。
これが「主人公」として生きるということなのです。
○「『ない』ところに、美を見つけ出そう。」(中谷彰宏)
現代アートに関わる者として、いちばん難しい質問は、
「どういうふうに鑑賞したらいいのですか?」というもの。
「いい!」と思えるかどうかはまさに感性の世界。
くさやを見て舌なめずりするかどうかは、その人次第のように。
当店店長の盛池は、駅のホームに「美」を見出します。
古い駅はホームの下層が煉瓦で、地層のように層を成す。
そこになんともいえない「美」を見出すのだそうです。
私にはとうてい理解できませんが、これこそ、
「ない」ところに「美」を見出すということなのでしょうね。