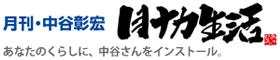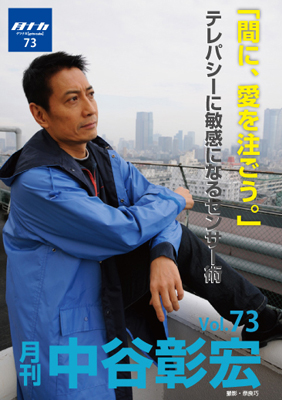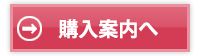月刊・中谷彰宏73「間に、愛を注ごう。」――テレパシーに敏感になるセンサー術
間が悪い人は、仕事でも人間関係でもうまくいきません。それは「間」に、その人の本質がすべて詰め込まれているからです。
「間」が悪い人には、3つの欠点があります。
○人の話を聴かない=強いジコチューさ。
○周囲に気を配らない=集中力の欠如。
○場の空気が読めない=低い社会性。
一方、「間」をしっかり掴めている人は違います。
○スポーツ、音楽、対話で鍛錬してきた。
○ビジネスの修羅場で戦ってきた。
○観察し気づき、自分を進化させてきた。
「間」が悪いままでは、歯車が合わない人生を送るだけ。
今こそ「間」を体得しましょう。
「間」の技術、中谷さんから教わりました。
★こんな方に有効です。
□「間」が悪い方。
□「間」の技術を修得したい方。
□「できない」と最初から諦めてしまう方。
○「間の悪い人は、センサーが弱い。」(中谷彰宏)
「間の悪さと運の悪さは別物。」と中谷さん。
つまり、「間」は、練習次第で改善できるというのです。
「間」の悪い人は、周囲の状況が見えていません。
何が起こるか、起こっているかを感知するセンサーが弱いのです。
このセンサーを強くするためにはどうしたらいいでしょうか?
それは「落ち着く」「集中する」「役割を考える」です。
逆を考えればわかりやすいですよね。落ち着きがなく、
気持ちが散漫になっていて、はしゃいでハメを外す……
「間」という問題意識に目覚めた瞬間、新たな修行が始まるのです。
○「『お約束』は愛。」(中谷彰宏)
働くということは、いい意味での「ごっこ遊び」。
平社員をしっかり演じられる。営業マンを演じられる。
役割に徹することができる人が、真のビジネスマンです。
彼らはビジネス社会における「間」を大切にします。
ビジネスにおける「間」とは、いわゆる「お約束」。
「お約束」をしっかり守れる人は、スムーズにことを運びます。
その態度は、お客さんや上司、同僚を幸せにします。
「お約束」を大切にできる人は、愛のある人なのです。
○「怒っている人は、間が悪い人。」(中谷彰宏)
間の悪い人とは、その場の空気がわからない人。
または、あえて、その場の空気を無視する人です。
彼らは会話の流れに乗れずに、言いたいことをしゃべります。
彼らは場のリズムに乗らずに、自分のペースを崩しません。
彼らは場のルールに従わずに、自分のやり方を押し通します。
当然、周囲の人たちとの軋轢が生じます。
「間が悪い人は、被害者意識が強い。」と中谷さん。
間の悪い人は、自分のことは棚に上げて周囲に怒りをぶつけます。
間の悪さは、コミュニケーションの大問題なのです。
○「パーティからは、黙って抜けよう。」(中谷彰宏)
飲み会やパーティでそろそろ帰ろうかというとき、
元気に「お先に失礼します!」と挨拶していませんか?
実はこれ、自分の礼儀正しさを優先した、空気が読めていない行動。
「帰ります宣言」をされたら「じゃあ、俺も」と場が揺らぎます。
せっかく盛り上がっていた場に、水を差すことになります。
宴会を抜けるときは、上手にフェードアウトするのが作法。
「間」のわかっている人は、いつのまにか消えているのです。
○「間がわかる人は、気配を消せる。」(中谷彰宏)
講演会などで、すでに演目が始まっているのに、
遅刻してきた人を丁寧に案内している会場係。
一見ホスピタリティあふれる仕事ぶりですが、
一段高いところから見れば、じつに「間」のわかっていない行動。
その行動は、講演者や聴衆の集中を妨げ、気を散らしているのです。
遅刻した人にしても、衆人環視のなか案内されるのは迷惑な話。
あえて放っておいてあげるのが、一段上のホスピタリティなのです。
○「ラジオで、間を学ぼう。」(中谷彰宏)
「間」のいい人は、「間」を体で学んできました。
「スポーツや音楽をやってきた人は、間がいい。」と中谷さん。
「間」というものは、高い身体性で発揮されます。
体を使いながら体得していく技法の一つです。
「ラジオを聴くと、間が良くなりますね。」と奈良さん。
ラジオこそ、まさに「間」が勝負の世界。
「間」が悪い掛け合いは、誰が聴いても一目瞭然。
私は、早朝のテレビ番組をお奨めします。
間の悪いシーンが続出で、反面教師として勉強になりますよ。
○「できているかではなく、目指している事が大事。」(中谷彰宏)
以前、早起き本を書かれた著者さんが言っていました。
「365日、4時起きというわけではありませんよ。原則4時起き。
毎朝4時に起きようとしていますが、当然、無理な日もあります。」
この話を聴いたとき、私は目から鱗が落ちました。
早起きを目標として生きる「ライフスタイル」が重要であり、
早起きそのものに執着する必要はないのだと悟ったからです。
「本に書いてあるからといって、全部できているわけじゃない。
できているかではなく、目指している事が大事。」と中谷さん。
理想の実現を目指して努力する。この心持ちこそが尊いのですね。