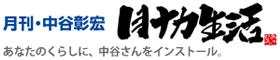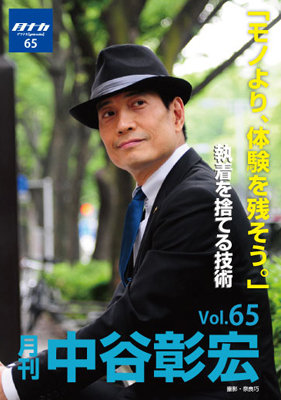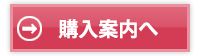月刊・中谷彰宏65「モノより、体験を残そう。」――執着を捨てる技術
運気が上がらないのは、捨てられないから。その執着を、神様は見逃しません。
あなたが執着すればするほど、神様はそれを奪い去ります。
でも、これは、奪ってあげることで、
幸せになってもらおうという、神様の粋なはからいです。
でも、奪われるのを待っていては、たいへんな時間のロス。
賢い人は、自ら進んで執着を手放しています。
そのためのマインドセット、中谷さんから伺いました。
★こんな方に、オススメです。
□捨てられない方。執着してしまう方。
□集中力が乏しく、無味乾燥な日々を送っている方。
□ツキがない方。
○「お守りは、借り物。」(中谷彰宏)
お守りは、神社からの借り物です。
借りたお守りは、神社にお返しするのが作法です。
モノも同じ。借り物なのです。
いつまでも、退蔵していてはバチが当たります。
使わないモノ、いらないモノは、輪廻させましょう。
手元から離れた時、そのモノは、
思い出というより高い次元に昇華するのです。
○「モノより、体験。」(中谷彰宏)
モノに執着したのは、ひと昔前の消費者。
新しい消費者は、モノより、体験を優先します。
ソムリエが勧める高いワインより、安くても思い出のあるワイン。
高級ホテルより、昔住んでいた町を彷彿とさせる安宿。
より大きい、より高価という尺度ではなく、自分の体験がベース。
体験に根ざした物語にまさるものはありません。
○「執着を、神様が奪う。」(中谷彰宏)
執着とは、本来手放すべきななのに、手放せない心の迷走状態。
子供が30歳になっても、子離れできない母親。
給料が下がったのに、高級マンションに居座ろうとするサラリーマン。
執着する人たちに、神様は非情です。
トラブル、事故、病気――さまざまな苦境をもたらして奪ってゆきます。
奪われる前に手放せば、そのスペースに運気が舞い込みます。
執着という毒でおかされる前にさっさとリリース。
○「使い切って、捨てよう。」(中谷彰宏)
使い切って捨てれば、モノは成仏してくれます。
使い切っていなくても、「ありがとう」のひと言で、
モノは新しい命を得て、また新しく生まれ変わります。
「今年の桜を見よう。」と中谷さん。
今年の流行は、今年一年で終わり。
しっかり着て、すっかり捨てる。
これがファッションとのつきあい方の大原則です。
○「集中すれば、何かが残る。」(中谷彰宏)
仕事に没頭すれば、膨大な「副産物」が出現します。
プレゼンで使った書類。
書き殴った企画メモ。
集めた資料のコピー。
こういったモノを記念にとっておいてはダメ。
潔く捨てましょう。
そうすることで、「集中」という至福の歴史が人生に刻まれるのです。
○「持つと、欲しくなくなる。」(中谷彰宏)
年間パスポートを買うと、かえって行かなくなる。
回数券を買うと、かえって使わなくなる。
愛人を持つと、かえって会わなくなる(!?)。
「義務」になると、行きたくなくなるのが人情。
手に入れるまでの昂ぶりが、いちばんワクワクするんですね。
持つことで失われてしまう、ワクワクドキドキ。
この幸せな感情を持ち続けるためには、所有しないこと。
「モノにこだわると、モノに騙される。」と中谷さん。
所有にこだわらないと、こんなに豊かに。
○「飾らないで、使おう。」(中谷彰宏)
モノは使われてはじめてオーラを発します。
美しい花瓶にしても、花が生けられずに、飾られては無意味。
重厚な南部鉄瓶にしても、使われてこそ価値が生まれます。
骨董だろうと、美術品だろうと、モノは使われこそ。
いい靴だから、かっこいいクルマだからと飾りませんよね。
モノは使われることで、生き生きしてくるのです。